 つむじ風
つむじ風 急な竜巻から身を守る・5月6日 茨城県で竜巻による死者
2012年5月6日、茨城県つくば市で発生した竜巻は、多くの家屋を破壊し、尊い命を奪いました。このような竜巻は、発生の予測が難しく、私たちが日常の中で直面する可能性のある自然災害です。この記事では、過去の事例を振り返りながら、竜巻から身を守るために知っておきたい備えと対策について紹介します。
 つむじ風
つむじ風  台風
台風 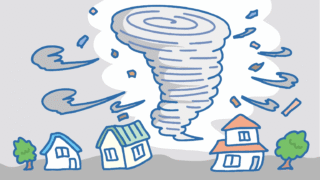 つむじ風
つむじ風 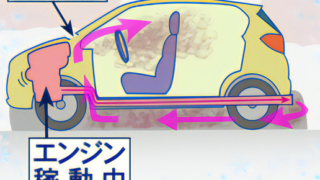 気象災害
気象災害  台風
台風  気象災害
気象災害  台風
台風 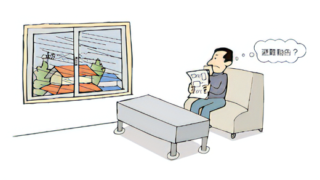 大雨
大雨  台風
台風  つむじ風
つむじ風