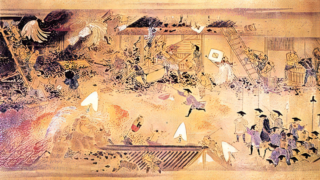 火災
火災 火災、出火原因と対策を考える・4月1日 明和の大火
火災は私たちの暮らしに潜む危険のひとつです。歴史を振り返ると、江戸時代の「明和の大火」のように、一つの火種が大惨事につながる例も少なくありません。本記事では、火災の主な原因や対策について紹介するとともに、私たちが日常生活でできる防火対策を考えます。
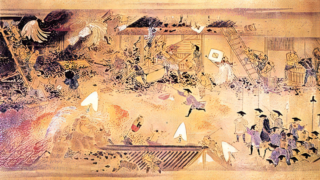 火災
火災  地震
地震  気象災害
気象災害  大雨
大雨  気象災害
気象災害  火山
火山  備蓄
備蓄  地震
地震  気象災害
気象災害  火災
火災