 土砂災害
土砂災害 豪雨による土砂災害への心構えを考えてみる・7月18日~19日 昭和39年7月山陰北陸豪雨
1964年(昭和39年)7月、梅雨前線の停滞により山陰・北陸地方を襲った記録的豪雨は、土砂災害を引き起こし多くの犠牲者を生みました。この記事では「昭和39年7月山陰北陸豪雨」の概要と、その教訓から学ぶ防災対策について解説します。突然の災害に備え、自分と家族の命を守るために何ができるのかについて考察します。
 土砂災害
土砂災害  気象災害
気象災害  台風
台風  大雨
大雨  大雨
大雨 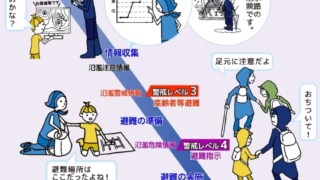 大雨
大雨  大雨
大雨  台風
台風  つむじ風
つむじ風  台風
台風