1806年に発生した「文化の大火」では、江戸の町が広範囲にわたり焼失し、多くの人々が住まいを失いました。このとき幕府が設けた「御救小屋」は、現代の避難所や仮設住宅の原型とも言える存在です。この記事では、歴史的な災害対応をひもときながら、現代における「避難場所」「避難所」「仮設住宅」の違いや役割について考えていきます。
幕府の建てた御救小屋(おすくいごや)
1806年4月22日(文化3年3月4日)江戸・文化の大火
文化の大火は、別名車町火事、あるいは丙寅火事ともいわれる江戸三大大火の一つとされています。
火災の原因は不明ですが、火災は同日10時頃、芝車町(現在の港区高輪2丁目)の材木座付近で発生しました。火災は折からの南風にあおられて北上し、日本橋、京橋、神田、浅草方面まで延焼拡大しました。
御救小屋(おすくいごや)とは
この火災で1,200人余りが死亡し、武家屋敷や寺社160棟余、江戸の530余町が焼失したとされています。
焼け出された人を救うため、幕府は御救小屋(おすくいごや)を建て、多数の人が仮の宿と食事をすることができるようにしました。

仮設住宅、避難場所と避難所
御救小屋とは、江戸時代に地震・火災・洪水・飢饉などの天災の際に、被害にあった人々を救助するために、幕府や藩などが立てた公的な救済施設(小屋)になり、現代では仮設住宅或いは避難所にあたると言えます。
仮設住宅とは
住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない人に対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図るものです。
参照 内閣府防災情報資料( 応急仮設住宅)より
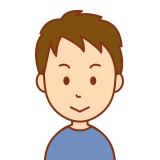
避難場所と避難所
東日本大震災時においては、避難場所と避難所が必ずしも明確に区別されておらず、そのことが被害拡大の一因ともなりました。そのため、内閣府は平成25年に災害対策基本法を改正し、市町村長は指定緊急避難場所及び指定避難所を区別してあらかじめ指定することとなりました。
避難場所(指定避難場所)とは
津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する施設又は場所を位置付けるものになります。
避難所(指定避難所)とは
避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設となっています。

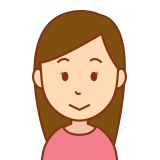
避難場所と避難所
どちらに行けばよいかご存知ですか?
まとめ
地震等の大規模な災害が起こった際に、避難する人々への対応が準備、検討されています。
幕府や各地の藩は御救小屋を準備しました。今は仮設住宅があり、さらに住民の生命の安全の確保のための避難場所、一時的に滞在するための避難所と過去の災害の経験をもとに対応が図られています。
いざ自分が災害に遭い避難する際に、どこへどう避難するかを事前に心得ておくことも自分自身の防災力アップに有効です。



