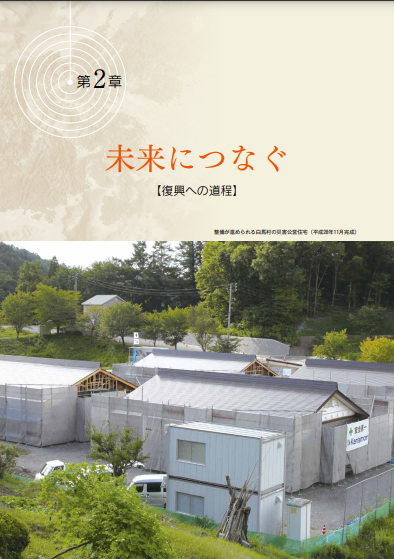2014年に発生した長野県神城断層地震では、迅速な救助活動が行われ、負傷者は出たものの死者はありませんでした。この地震で注目されたのが、住民同士の「共助」によるスムーズな災害対応です。山間部の集落でも孤立することなく、早期の安否確認が可能だったことで、行政や公的機関は「公助」に集中でき、全体的な対応が円滑に進みました。この記事では、「自助」「共助」「公助」という災害時の重要な3つの支えについて、その役割と重要性を考えます。
迅速な救助活動
2014年(平成26年)11月22日 長野県神城断層地震

長野県北部を震源とするマグニチュード6.7の地震が発生し、長野県を中心に46人が負傷、家屋損壊は2,000棟以上に及んだが、迅速な救助活動もあり、死者ありませんでした。
「共助」の効果で災害対応全般がスムーズに
「共助」の効果で災害対応全般がスムーズに
地震が夜間に発生したにもかかわらず、人的被害の情報が早い段階で把握できたことや、山間部の集落でも完全な孤立が発生しなかったこと、そして安否確認が早く、連絡がつかない人がいなかったことは幸運だった。
通常の災害であれば大きな労力が割かれる部分がスムーズに進んだ背景には、住民同士の助け合いによる「共助」が機能したことが大きかった。共助の効果で結果的に役所は本来の「公助」に集中できるようになり、災害対応全般がスムーズに流れる効果を生み出すことになった。もちろん、広い範囲で大きな被害が出なかったことも幸いだった。
被災エリアが広くなれば、災害対応はどうしても人海戦術にならざるを得ず、人的リソースの不足を露呈していたかもしれない。連絡を取り合うにあたり、携帯電話が使えたことも大きい。そして県が情報連絡員を市町村に派遣したこともいい形で作用した。
出典 長野県|長野県神城断層地震災害記録集
大規模災害時では、公的機関による「公助」の機能に限界がある場合があります。
いざという時には自分で自分の命を守る「自助」、近所の人や知り合いなどがお互いに助け合う「共助」が災害対応では大事になります。
自助、公助、共助とは
災害への備えを考えるとき、「自助」「共助」「公助」の3つに分けることができます。 「自助」とは、災害が発生したときに、まず自分自身の身の安全を守ることです。この中には家族も含まれます。
「共助」とは、地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力して助け合うことをいいます。
そして、市町村や消防、県や警察、自衛隊といった公的機関による救助・援助が「公助」です。
出典 総務省消防庁|eカレッジ
自助、公助、共助という三つの“助け”!
scene 06
自助、公助、共助という三つの“助け”!
「一つめは、『自助(じじょ)』。家具がたおれないように固定(こてい)したりして、自分で自分の命を守ること。二つめは、『公助(こうじょ)』。国や県、市や町などの公共機関(こうきょうきかん)による助けだ。そして三つめは、近所の人や知り合いなどがおたがいに助け合うこと。これを、『共助(きょうじょ)』と言うぞ。自助、公助、共助。被害(ひがい)を最小限(さいしょうげん)におさえるためには、この三つの“助け”がかかせないんだ!」とドスルが言いました。「これならみんなの命は守れるね!」とコスル。するとドスルが、「いざというときに、本当に地域(ちいき)で助け合えるかが問題なんだ」と言います。
出典 NHK for Shool|どうする?大災害が起きたら

自助・共助・公助の役割について
災害時に重要となる 自助・共助・公助について、それぞれの役割を解説しています。
出典 himejicitych
大規模災害時の「公助の限界」
阪神大震災や東日本大震災、西日本豪雨災害による水害など、大規模災害時では公助(行政、消防、警察、自衛隊、医療機関)の機能に限界があります。また、道路や交通手段に大きな被害が出ると、物資を運ぶ物流も機能低下します。
災害からの被害をできる限り少なく抑えるためには、平常時から、自ら取り組む自助、地域で取り組む共助を実施し、大規模災害に備えることが必要になります。
出典 三田市|自助、共助、公助でいざという時に備えましょう
まとめ
大規模災害時では行政、消防、警察、自衛隊、医療機関も被災し、公助が機能するまでに時間がかかる場合があります。災害時は自分自身で取り組むと同時に、近所の人や知り合いなどがお互いに助け合えるように普段からの共助が必要です。
人のつながりに助けられた
平成30年7月豪雨(平成30年7月)
叱ってくれた近所の方に感謝
倉敷市 40代 女性
被災直後、水が引くまでは自宅を確認することができませんでした。ニュースや様々なところで飛び交う情報から不安になり、どうすれば自宅まで行けるのか、自宅がめちゃくちゃだったらどうしたらいいのだろうと、あれこれ考える毎日でした。数日後、やっとたどりついた自宅の悲惨な状況に、本当にがっくりと力尽き、何も考えられず、何かをする気力も失ってしまいました。
そんな時、近所の方が「しっかりしなくちゃ!」と叱ってくれたのです。そして、その方も被災していたのですが、そのご家族や、ママ友、東日本大震災を経験した主人の同僚など、様々な方が暑いなか、ドロドロになった家の片付けを丁寧に手伝ってくれました。
誰かがいてくれるとやる気になる。手伝ってくれると頑張ることができました。本当に、人のつながりに助けられたなと、つながりって大事だなと実感しました。
出典 内閣府防災情報のページ|一日前プロジェクト