2005年12月25日、山形県庄内町で発生した「羽越本線特急列車脱線転覆事故」では、特急列車が突風にあおられ脱線、車両が転落するという惨事が起こりました。また、台風や竜巻などによる暴風も、家屋の被害や日常生活の混乱を引き起こします。本記事では、過去の災害事例や気象現象に潜む危険性を振り返り、突風への備え方について考えます。自然の脅威に正しく備えることで、被害を最小限に抑える術を探りましょう。
突風にあおられ脱線
2005年(平成17年)12月25日 羽越本線特急列車脱線転覆事故

山形県庄内町のJR羽越本線・北余目~砂越駅間で、秋田発新潟行きの特急「いなほ14号」が最上川橋梁通過後の盛土区間を走行中に突風にあおられ、6両編成の全車両が脱線、うち先頭から3両が盛土から転落・横転し一部の車両が進行方向左側の建物に衝突しました。
突風で電車が脱線することもあります。たかが風だと侮らずに気象災害としてその対応を心がけておくことが身の安全を図る上で大事です。
突風の被害
突風は平らな場所で発生しやすく、日本では東北地方の日本海側から北陸にかけて、関東地方から九州の太平洋側、沖縄で発生確認数が多くなっています。
自動車を巻き上げる突風のすさまじさ
8月3日の郡山市の突風は竜巻だった 福島地方気象台が発表 (2023年8月5日)
出典 福島中央テレビ
暴風による被害
令和元年房総半島台風で最も大きな被害をもたらしたのは、暴風です。千葉市では、最大風速35.9メートル、最大瞬間風速は57.5メートルを記録。関東地方を中心に19地点で観測史上1位となる最大風速や最大瞬間風速を記録しました。
暴風が被災地の住民にもたらした大きな障害が、家屋の屋根への被害です。千葉県を中心に、多くの家で屋根が飛ばされる、穴が開くといった被害が続出しました。
出典 総務省消防庁|防災・危機管理eカレッジ|令和元年房総半島台風
予兆を見逃さないで身を守る
災害から身を守る為には予兆を見逃さず、その対応を考えておくことが必要です。
何かが起こる前の予兆
館林市の竜巻(平成21年7月)
急な気温の変化は何かが起こる前の予兆と心にとどめる
館林市 50代 男性 会社経営
竜巻の起こった日は昼過ぎにぽつぽつと雨が降り出し、少ししてから強い風が吹き始めたのを覚えています。今思い起こしても、何の前触れもない夏の日の午後だったと思います。ただ思い返せば、竜巻の発生した日、あの日の朝の天気予報では「突風注意」と表示されていました。しかし、上州(じょうしゅう)は「からっ風」でも有名なところで、だれもが「風」には慣れっこになっている。そのせいか、だれもが大して気にもとめなかったのだと思います。
竜巻の発生前には、真夏であっても急に気温が下がり、涼しさと空気が止まったような静けさを感じたのを覚えています。あれが前触れだったといえるのでしょう。あの朝、前橋気象台が出した情報にもう少し注意していれば被害を軽減できたかもしれない。これも結果論ですが、自然災害の脅威に私たちはもう少し敏感でなければならないと思います。
出典 内閣府防災情報のページ|一日前プロジェクト
急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう!
積乱雲が近づいてきたサインに気づかなかったことや、自然現象の恐ろしさに対する油断があったことが原因で、子どもたちが次々に災害に遭います。
視聴することで、なぜ映像の子どもたちは危険な目にあってしまったのかを考えるきっかけを提供します。
出典 気象庁|防災啓発ビデオ「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう!」
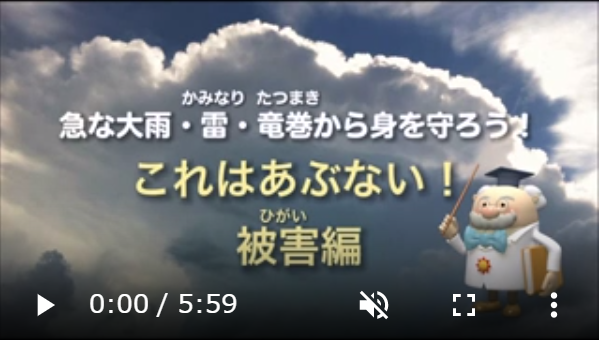
突風や竜巻の対策 その原因や前兆、被害を防ぐには?
周辺が急に暗くなった。冷たい風が吹いた。それは積乱雲が近づいている証拠。突風や竜巻が発生する危険があります。鉄筋コンクリートの建物に逃げ込んで下さい。突風や竜巻から身を守る方法をまとめています。
出典 NHK|災害列島 命を守る情報サイト

まとめにかえて
突風は、台風や竜巻などの気象現象によって発生することがあります。突風が発生すると、列車や車でもあおられることがあり、また屋根や壁、看板やバルコニーなどの建物の一部が破壊されたり、飛散したりする危険があります。
突風が発生したときは、頑丈な建物に避難し、窓から離れた部屋や、クローゼット、風呂場の浴槽に移動するとより安全です。窓がある部屋の場合は、ガラスの飛散を防ぐためにカーテンを閉めて机の下などで頭を守ることが必要です。




