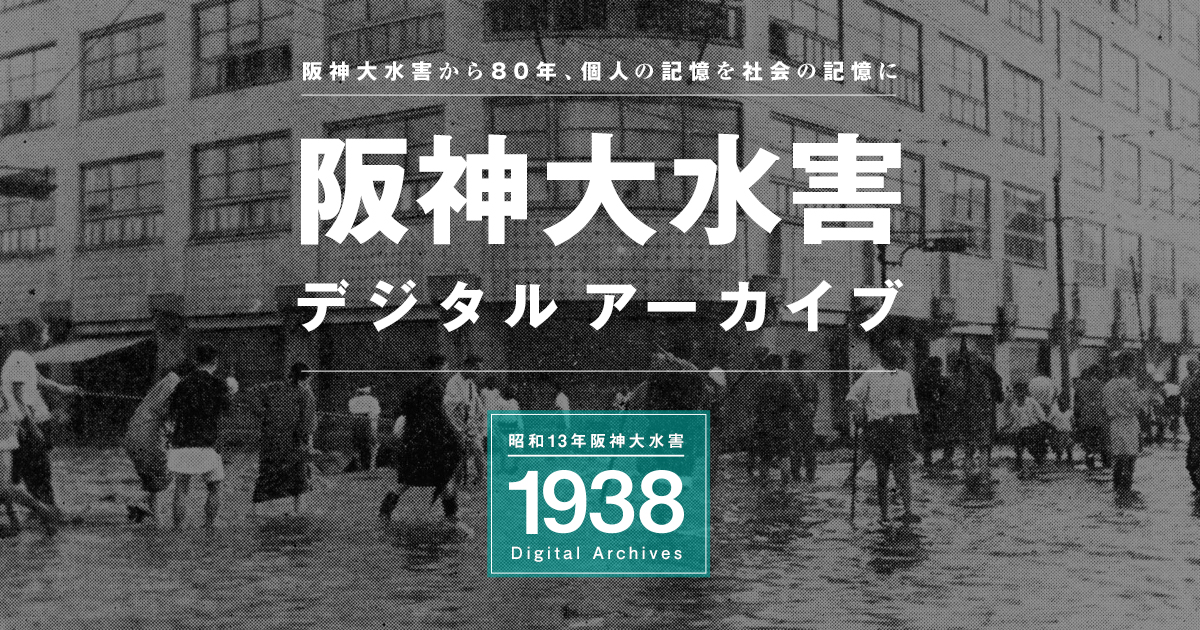1967年7月、西日本の都市部を中心に記録的な大雨が襲い、土砂災害や鉄砲水により甚大な被害が発生しました。昭和42年7月豪雨として記録されたこの災害は、都市の脆弱性と砂防対策の重要性を改めて突きつけました。
都市部の大雨で土砂崩れや鉄砲水が発生
1967年(昭和42年)7月7日から10日にかけて 昭和42年7月豪雨

本州南岸に停滞する梅雨前線と台風7号から変わった温帯低気圧の影響で、西日本を中心に大雨となりました。
特にこの大雨では都市部で大雨となったことが特徴で、1時間降水量は長崎県佐世保市で125mm、長崎県福江市(現在の五島市)で114mmを観測したほか、広島県呉市や兵庫県神戸市でも70mmを超え、2日間降水量は300mmを超えた。これらの都市は、いずれも市街地の背後に山が迫っていることが特徴で、大雨によって土砂崩れや鉄砲水が相次いで発生しました。

土砂災害から命を守るには
地滑り・土石流・崖崩れ ハザードマップでリスクをチェック
「土砂災害」で警戒すべき点は?地滑りや土石流、崖くずれなどの土砂災害により、大きな被害が出ています。土砂災害警戒情報など、避難の際に参考になるポイントを紹介します。
出典 NHK防災

被害軽減に寄与した砂防事業
昭和13年阪神大水害を受け、神戸市に内務省六甲砂防事務所が開設され、国による河川改修と砂防事業が始まりました。
出典 国土交通省|昭和42年六甲山系豪雨災害

昭和42年7月豪雨による災害時には、住吉川など六甲山系を水源とする河川の中上流域には174基の砂防堰堤が設置されていました。これにより市街地に流れ出す土砂の量は、昭和13 年阪神大水害と比較して大幅に減少し、被害が抑制されたといえます。
さらに、平成30年7月豪雨による雨量は、昭和13年、昭和42年の豪雨災害に匹敵するものでしたが、その時点で設置された砂防堰堤545基や斜面対策・樹林整備の効果により、人的被害はありませんでした。
まとめにかえて
昭和42年7月豪雨(1967年7月7日〜10日)は、梅雨前線と台風の影響により西日本を中心に大雨となり、特に都市部での被害が目立ちました。
長崎県佐世保市では1時間に125mmの雨を観測するなど、記録的な降雨があり、背後に山を抱える都市で土砂災害や鉄砲水が多発。死者・行方不明者は369人、家屋の損壊・浸水は30万棟以上にのぼりました。
神戸市では、昭和13年の阪神大水害を教訓に整備された砂防堰堤が効果を発揮し、被害軽減に寄与。近年の豪雨でも砂防設備や斜面対策により人的被害を防ぐ成果が見られています。