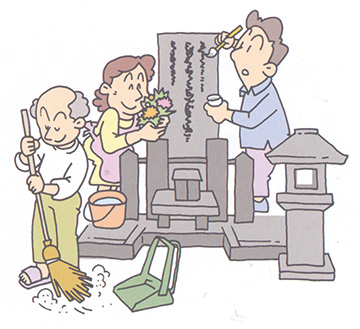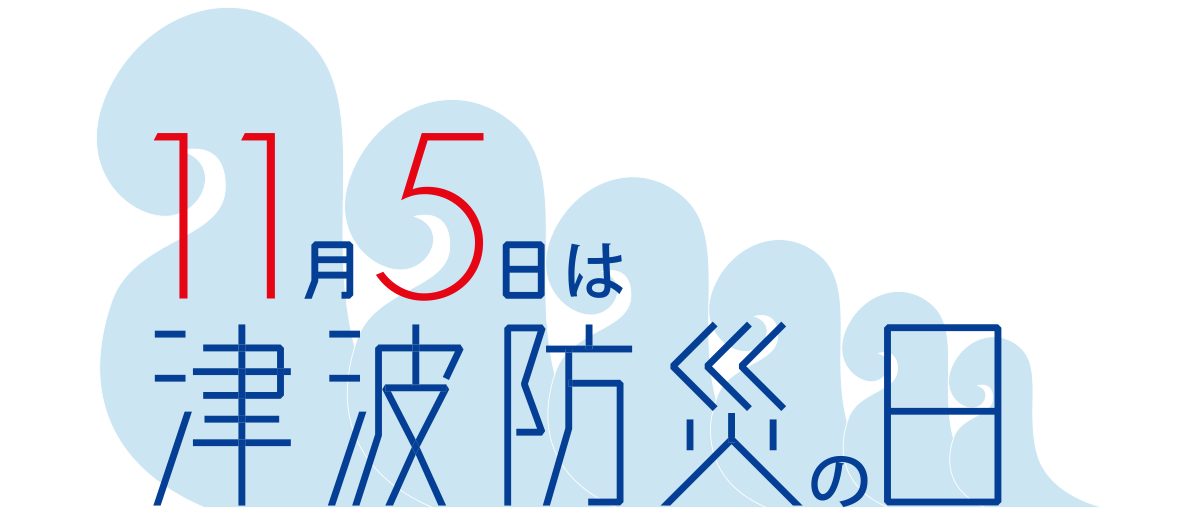11月5日は、津波防災の日として国際的に認識されています。この日は、1854年に発生した安政南海地震による大津波をきっかけに、日本の和歌山県で起きた「稲むらの火」の逸話に由来しています。勇敢な行動で村人たちの命を救ったこの出来事は、津波に対する防災の重要性を象徴しています。現在、津波のリスクは日本だけでなく、世界各地で問題となっており、津波から命を守るための意識向上と防災対策が求められています。
地震による大津波が発生
1854年(嘉永7年)11月5日 安政南海地震による大津波
11月5日は、嘉永7年(1854年)、安政南海地震(M. 8. 4)による大津波が紀伊半島を襲った日です。
その際、和歌山県のある村の郷士が、収穫したばかりの穂を積み上げた「稲むら」に火を放って、暗闇の中で逃げ遅れた村人を高台に導き多くの命を救ったという出来事がありました。
この「稲むらの火」の逸話に因んで「津波防災の日」として11月5日が選ばれました。(太陽暦では、1854年12月24日)
出典 津波防災特設サイト
津波防災は世界中に広がっています
1960年のチリ、1976年のフィリピン、1998年のパプアニューギニア、1999年のトルコ、2001年のペルー、2004年のインド洋沿岸諸国、2009年のサモアおよびトンガ沖、そして、2011年の東日本大震災など、世界各地で津波被害が発生しており、津波の脅威は多くの世界共通の課題となっています。
出典 内閣府ホームページ 津波防災特設サイトより 津波発生源
日本では、2022年に「津波防災の日」を法定
日本では、東日本大震災が発生した2011年に、津波対策について国民の理解と関心をより一層高めるために、法律で「津波防災の日」を制定し、全国各地で津波防災訓練や意識啓発の取り組みを実施しています。
出典 内閣府ホームページ 津波防災特設サイトより
津波から命を守る
大地震はいつ来るかわかりません。 その時どうすればいいか、日頃から考えておきましょう。
津波はすごいスピードで迫ってきます。 津波が来たら何も持たず、各自が全力で逃げてください。
2つのお約束
・家族と逃げる場所を決めておく
・自らの命を守ることに全力を尽くす
出典 津波防災特設サイト
「“逃げない自分” を知ること」が備えの第一歩
多くの犠牲者を出した12年前の東日本大震災。千島海溝・日本海溝や南海トラフで発生が危惧される巨大地震では東日本大震災を上回る被害の想定も。私たちが命を守るためにどう備えればいいのか?皆さんは、“逃げない自分”について、知っていますか?
出典 NHK防災
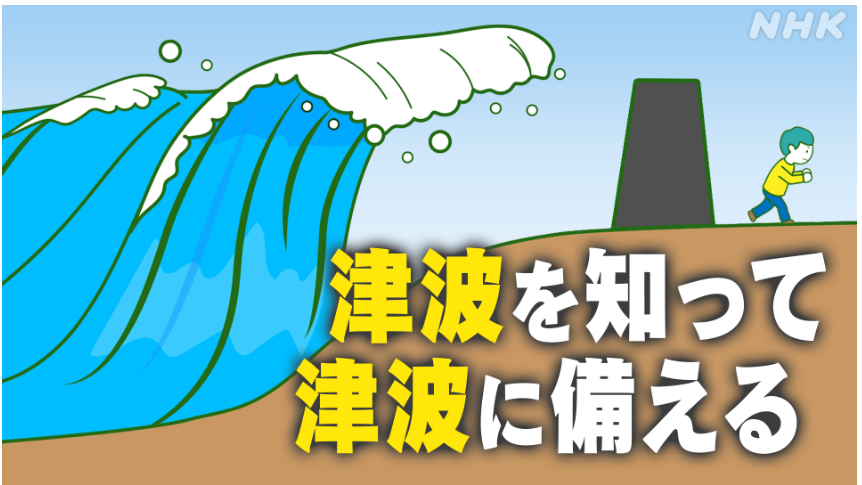
11月5日は津波防災の日
■「過去に学びいま備える」
安政南海地震が発生した11月5日が法律で定められた「津波防災の日」です。
今後、発生が懸念される南海トラフ巨大地震では、岡山・香川にも2メートルから4メートル程度の津波が到達する想定です。
また、干拓地などでは液状化も想定され、避難の妨げになる可能性もあります。
そこで押さえてほしい備えのツボはこちら。巨大地震はいつか必ずやってきます。11月5日は津波防災の日。ハザードマップでリスクを確認し、家族と避難経路などについて話し合いましょう。
出典 OHK公式チャンネル
まとめにかえて
災害は忘れた頃にやって来ると言われますが、忘れていなくても油断した時にやって来ることもあります。
今自分がいる場所は過去に被災したことがあり、そこから復旧復興して現在があるかもしれません。過去被災した人たちからの、メッセージを見逃さないでおくことも防災に取り組む上で大事なことです。
安政南海地震津波(1854)
江戸時代の終り、1854(安政元)年12月24日、大阪の町中を津波が襲いました。大阪は「水の都」といわれ、町の中を何筋もの川が通り、川にはたくさんの橋が架けられていました。
津波は港の大船を川筋に沿って押し上げ、川の小舟に避難していたたくさんの人々の命を奪いました。これは、四国沖の海底で発生した大規模な地震によって引き起こされたもので、安政南海地震津波と呼ばれています。
出典 内閣府防災情報のページ|災害を語りつぐ 3

犠牲者の供養と災害の体験を伝える石碑
この津波によって大阪で亡くなった人は341人といわれています。当時の人たちは150年前の津波の経験を忘れたために、再びたくさんの人が亡くなったことを悔やみました。そして、後世の人たちが大阪も津波に襲われることを忘れないように、言い伝えを残すことにしました。それには風雨にさらされて刻んだ文字がわからなくなることのない石に文字を刻んで、多くの人が目につくところに建てておくのがよいと考えました。
その碑文の最後には、これからの人たちがこの悲劇を繰り返さないように、そして、石に刻んだ警告の言葉は薄れてしまうから、毎年墨を入れてはっきりとわかるようにしておくことも刻み込まれています。この石碑は現在、大阪市浪速区幸町3町目の大正橋東詰北側の歩道にあります。今も地域の人たちが石に刻まれた教えを守り、墨を入れて文字が消えないように石碑を守っています。