江戸の大火
1657年3月2~3日 明暦の大火
明暦3年(1657)正月18日(1657年3月2~3日)本郷丸山本妙寺から出火し、翌19日には小石川伝通院前と麹町からも出火。3件の出火によって江戸城本丸、ニノ丸、三ノ丸はじめ武家邸500余、寺社300余、倉庫9,000余、橋梁61を焼失、死者10万余人ともいわれ、江戸の町の大半が焦土となったほどの大惨事でした。
ぼやで身を焼く八百屋お七
お七火事といわれるものには、天和2(1682)年1月27日の火事と同年12月28日および天和3(1683)年3月2日の火事(『天和笑委集』)説があり、現在のところはっきりしていません
出典 東京消防庁ホームページ
江戸の都市防災
江戸幕府の都市防災の取り組みは以下のようなものがあります。
・防火用水の常備
・火消組織の強化
また、都市構造の火災への強化としての取り組みもありました。
・火除地以外にも大通り「広小路」や防火堰を配置
・町並みの間を大きくとる
・堤の上に気を植え防火林とする
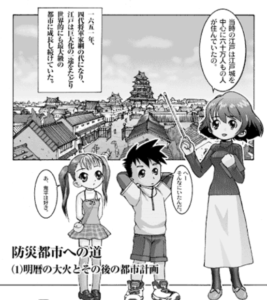
江戸時代、火災は恐ろしい災害で様々な伝承として語り継がれています。大きな災害を後の人達に伝えようという気持ちは、現代にも伝わります。
都市防災について
国土交通省が取り組む防災まちづくり
首都直下地震、南海トラフ巨大地震などの発生が想定されていますが、地震だけに限らず、最近では大雨や大雪など自然災害も頻繁におこっており、日ごろからの備えが必須となってきました。
激化する災害に備える
近年、激化する大雨や噴火により甚大な被害をまたらす自然災害が頻発しています。また、首都直下地震や南海トラフ大地震は30年以内に約7割の確率で発生するとも想定されており、災害への備えは待ったなしの状況です。
国土交通省では、道路・堤防・橋・トンネル・都市公園・下水道など、私たちの生活を支える社会基盤の整備や維持・補修に関する業務を幅広く担っており、災害に備えたこれらインフラの整備や老朽化対策を進めています。
一方で、東日本大震災の教訓も踏まえて、このようなハード面の対策に加えて、災害が起きたときにひとり一人がすぐに命を守るための適切な行動を取れるよう、災害リスクの高い場所の周知や避難訓練の実施など、ソフト面の対策への支援にもより一層積極的に取り組んでいます。
出典 「国土交通」No.131(2015.4-5) – 国土交通省 特集「都市防災」
まちを歩いて防災マップを作ろう
地震や火災、洪水などの災害が起こると、普段見慣れているはずのまちの姿が一変し、思いもよらない事態に遭う場合があります。例えば、避難場所がどこかはわかっているのに、そこにたどりつく道がわからなかったりすることも・・・

そのためにも、日ごろから自分のまちをよく知ることが重要。
まちを歩いて防災マップをつくることがおすすめです。
「住んでいる地域で災害が起きたら・・・」ということを意識しながら、地域の状態や危険な場所などを、家族や地域の人たち、学校のお友達などと一緒に歩いて確認し、 – 自分たちのまち専用の防災マップ”をつくってみましよう!
出典 「国土交通」No.131(2015.4-5)|特集 都市防災
まとめにかえて
防災まち歩きは、自分が住む地域の防災上の特性を把握することを目的に行われるものです。まちあるきをするエリアやルート、テーマ(点検する項目)を決め、実際にまちを歩きます。まちの中の危険箇所や防災設備・史跡などを探すことで、災害を他人事ではなく捉えることができます。
災害に強い街とは、同じ強さの地震がきても被害が少なくなる街、被害を出さない街、そして被害が出ても地域の人たちが対応して、すぐにみんなで助け合って災害を乗り越えていく街を指します。
まちあるき防災マップをつくると・・・
・見慣れてりうまちの中で災害のとき危険な場所がわかる
・いざというときにすばやく避難できる
・一緒に作業することで顔見知りになる人が増えるかも
出典 「国土交通」No.131(2015.4-5)|特集 都市防災





